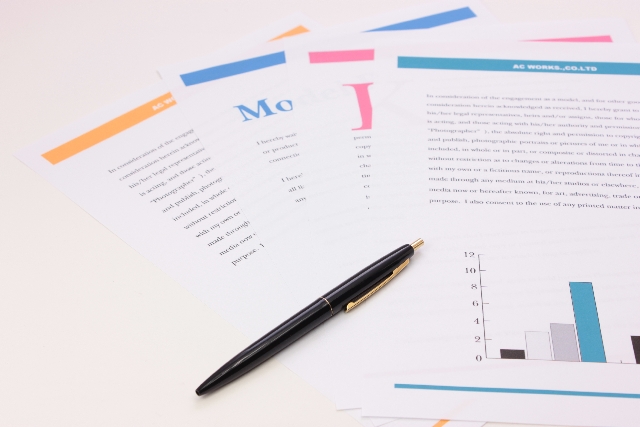


自己都合退職の特定理由離職者の場合、
給付制限はかかりませんが、
場合によっては給付日数が会社都合同様、延長されることはありますか?
給付制限はかかりませんが、
場合によっては給付日数が会社都合同様、延長されることはありますか?
個別延長給付のことを言ってるのか、所定給付日数のことを言ってるのかわかりませんが、個別延長給付は元々求人の少ない地域であるとか、災害などの被害に遭ったことで再就職が難しくなった地域であるとか、最低限の就職を目指すのにも技量が足りなくて更なる職業訓練などを行わなければいけないと判断された場合など、ハローワークが必要であるとした時に延長されるものなので、受給資格さえ得られれば就職困難者を除いて誰にでも可能性だけはあります。
就職困難者の場合は所定給付日数が大きく延長されているので特定受給資格者であっても個別延長はありません。
特定受給資格者の場合はより手厚い支援をしましょうってことで最初から個別長給付の候補になっていますが、所定給付日数に応じた求人への応募回数が足りなかったり、失業認定の際に不認定になったり、指示された職業訓練や求人への応募を拒否したりなどなどをすると個別延長給付がされないこともあります。
所定給付日数が延長される場合は二通りあります。
有期契約の期間満了で退職した時に契約の更新がほぼ無条件で更新されるのではなく、何らかの条件を満たせば更新されることがあるなどとされている場合は特定理由離職者ということになりますが、受給資格の中身としては特定受給資格者と同じものになり、所定給付日数も特定受給資格者と同じということになります。
もうひとつは特定理由離職者に相当する理由であっても「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」を満たせずに「離職前1年で6か月以上の被保険者期間があること」を満たしたことで受給資格を得られる場合です。
「離職前○年で×カ月以上の被保険者期間がある」という条件は病気やけがで休職していたり、育児休業などを取っている間は「離職前○年」に勘案しません。ただし、全部を勘案しないわけではなく、勘案しない期間にも上限があります。
「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」の場合は「離職前4年」と読み替え、「離職前1年で6か月以上の被保険者期間がある」の場合は「離職前2年」と読み替えます。
たとえば、被保険者として5年働いていた方が6年目の2カ月経過後に病気などで2年6か月休職をしていったん復帰し、復職の6か月後から育児休業を1年取ったまま何らかの特定理由離職者に相当する個人的な理由で退職をしたとします。退職時の満年齢は29歳とします。
ただし、話が面倒くさくなるので、復帰した6か月間で各月で被保険者期間が1か月ずつあると仮定し、育児休業給付を受け取っていないという前提にします。
これを被保険者期間の条件に当てはめる場合、退職直前の1年の育児休業を取得していた期間をまずは除きます。さらに復帰する前の2年6か月の休職期間も除くので、離職前4年では被保険者期間は6か月ということになり、2年を4年と読み替えた後の「離職前4年で12カ月以上の被保険者期間がある」を満たせません。
そこで、今度は「離職前1年で6か月以上の被保険者期間がある」を見に行くと、今度は「離職前2年」と読み替えますから、「離職前2年で6か月以上の被保険者期間がある」は満たせることになり、特定受給資格者と同じ所定給付日数ということになります。
被保険者として在籍していた期間には休職をしていた期間も育児休業していた期間も含む(育児休業給付をもらわない前提)ので、5年2カ月+2年6か月+6か月+1年=9年2カ月が所定給付日数を決める算定基礎期間ということになり、退職時の年齢が29歳ですから、所定給付日数は0歳未満で5年以上10年未満の120日ということになります。
なお、育児休業をして育児休業給付を受け取っていると育児休業給付を受け取った日は一日単位で算定基礎期間から除かれます。
就職困難者の場合は所定給付日数が大きく延長されているので特定受給資格者であっても個別延長はありません。
特定受給資格者の場合はより手厚い支援をしましょうってことで最初から個別長給付の候補になっていますが、所定給付日数に応じた求人への応募回数が足りなかったり、失業認定の際に不認定になったり、指示された職業訓練や求人への応募を拒否したりなどなどをすると個別延長給付がされないこともあります。
所定給付日数が延長される場合は二通りあります。
有期契約の期間満了で退職した時に契約の更新がほぼ無条件で更新されるのではなく、何らかの条件を満たせば更新されることがあるなどとされている場合は特定理由離職者ということになりますが、受給資格の中身としては特定受給資格者と同じものになり、所定給付日数も特定受給資格者と同じということになります。
もうひとつは特定理由離職者に相当する理由であっても「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」を満たせずに「離職前1年で6か月以上の被保険者期間があること」を満たしたことで受給資格を得られる場合です。
「離職前○年で×カ月以上の被保険者期間がある」という条件は病気やけがで休職していたり、育児休業などを取っている間は「離職前○年」に勘案しません。ただし、全部を勘案しないわけではなく、勘案しない期間にも上限があります。
「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」の場合は「離職前4年」と読み替え、「離職前1年で6か月以上の被保険者期間がある」の場合は「離職前2年」と読み替えます。
たとえば、被保険者として5年働いていた方が6年目の2カ月経過後に病気などで2年6か月休職をしていったん復帰し、復職の6か月後から育児休業を1年取ったまま何らかの特定理由離職者に相当する個人的な理由で退職をしたとします。退職時の満年齢は29歳とします。
ただし、話が面倒くさくなるので、復帰した6か月間で各月で被保険者期間が1か月ずつあると仮定し、育児休業給付を受け取っていないという前提にします。
これを被保険者期間の条件に当てはめる場合、退職直前の1年の育児休業を取得していた期間をまずは除きます。さらに復帰する前の2年6か月の休職期間も除くので、離職前4年では被保険者期間は6か月ということになり、2年を4年と読み替えた後の「離職前4年で12カ月以上の被保険者期間がある」を満たせません。
そこで、今度は「離職前1年で6か月以上の被保険者期間がある」を見に行くと、今度は「離職前2年」と読み替えますから、「離職前2年で6か月以上の被保険者期間がある」は満たせることになり、特定受給資格者と同じ所定給付日数ということになります。
被保険者として在籍していた期間には休職をしていた期間も育児休業していた期間も含む(育児休業給付をもらわない前提)ので、5年2カ月+2年6か月+6か月+1年=9年2カ月が所定給付日数を決める算定基礎期間ということになり、退職時の年齢が29歳ですから、所定給付日数は0歳未満で5年以上10年未満の120日ということになります。
なお、育児休業をして育児休業給付を受け取っていると育児休業給付を受け取った日は一日単位で算定基礎期間から除かれます。
失業保険に関して何ですが、1月20日に会社を自己都合退職して3月16日に初回認定日だったんですが失業保険が貰えるまで三ヶ月かかるそうなんですが、
その間ってバイトとかは出来ないんですか?
その間ってバイトとかは出来ないんですか?
給付制限期間中のアルバイトについては可能です。但し、就職とみなされるようなアルバイトは出来ません。
給付制限期間中のアルバイトの基準に関しては、管轄のハローワークにより異なりますので、事前にハローワークと相談し、どこまでの労働時間、労働日数なら認められるのか確認して下さい。
給付制限期間中のアルバイトの基準に関しては、管轄のハローワークにより異なりますので、事前にハローワークと相談し、どこまでの労働時間、労働日数なら認められるのか確認して下さい。
介護休暇について教えてください。関東在住ですが、東北から介護認定1の父を3ヶ月程度引き取る事になりました。介護休暇をとりたいのですが、小さな事務所で私がずっと休んでいるわけにもいかず、近くに住む姉にた
まに来てもらったり等して出勤も可能です。
続けて休まなければ、介護休暇にはならないのでしょうか?
いろいろ調べたのですが、よくわからず宜しくお願いします。
まに来てもらったり等して出勤も可能です。
続けて休まなければ、介護休暇にはならないのでしょうか?
いろいろ調べたのですが、よくわからず宜しくお願いします。
労働局雇用均等課へ連絡してみてください。法律が施行されていますので、詳しく教えてくれます。
ただ、介護休業の取得と介護休業給付金(雇用保険)の支給は異なりますので、介護休業給付金についてはハローワークで確認してみてください。
育児介護休業法では、介護休業は対象家族1人に対して通算93日。通算できるのは同一家族について異なる症状による介護休業による。ともしています。極端な例であれば、介護状態が変わらないお父さんの介護のため、3日休んで1日出勤して、また休むという形が通算になる出あれば通算できなくなります。介護状態が変わらないお父さんの介護のために3ヶ月継続して休んだとすれば、通算93日ではなく、3ヶ月が限度ともしています。(どの月から3ヶ月継続して休んでも93日にはなりませんから)
介護休業給付金も同じで、対象家族1人に対して通算93日。通算できるのは同一家族について異なる症状による介護休業に限られています。こちらは、1ヶ月の間に10日以下の出勤であれば、1ヶ月出勤しなかったものとして給付金の支給をしてくれます。先に書いた極端の例でも1ヶ月10日以下の出勤になれば給付金の支給対象となりますが、一度復帰してしまうと、次は同じ症状での介護休業が会社でできたとしても、給付金は支給されません。
また、介護休業期間中は社会保険(健康保険、厚生年金)は免除になりません。自己負担分の支払いは発生します。
労働局に法律を、ハローワークで給付金を、会社にて介護休業の取得方法をそれぞれ確認してみてください。
ただ、介護休業の取得と介護休業給付金(雇用保険)の支給は異なりますので、介護休業給付金についてはハローワークで確認してみてください。
育児介護休業法では、介護休業は対象家族1人に対して通算93日。通算できるのは同一家族について異なる症状による介護休業による。ともしています。極端な例であれば、介護状態が変わらないお父さんの介護のため、3日休んで1日出勤して、また休むという形が通算になる出あれば通算できなくなります。介護状態が変わらないお父さんの介護のために3ヶ月継続して休んだとすれば、通算93日ではなく、3ヶ月が限度ともしています。(どの月から3ヶ月継続して休んでも93日にはなりませんから)
介護休業給付金も同じで、対象家族1人に対して通算93日。通算できるのは同一家族について異なる症状による介護休業に限られています。こちらは、1ヶ月の間に10日以下の出勤であれば、1ヶ月出勤しなかったものとして給付金の支給をしてくれます。先に書いた極端の例でも1ヶ月10日以下の出勤になれば給付金の支給対象となりますが、一度復帰してしまうと、次は同じ症状での介護休業が会社でできたとしても、給付金は支給されません。
また、介護休業期間中は社会保険(健康保険、厚生年金)は免除になりません。自己負担分の支払いは発生します。
労働局に法律を、ハローワークで給付金を、会社にて介護休業の取得方法をそれぞれ確認してみてください。
関連する情報